 悩める新人看護師
悩める新人看護師「夜勤、想像以上にきつい…もう限界かもしれない…」
「こんなに辛いのは私だけ?みんなはどうやって乗り越えてるんだろう…」
そんな風に慣れない夜勤に戸惑い、不安で押しつぶされそうになっていませんか?
大丈夫ですよ。その気持ち、痛いほどよく分かります。何を隠そうこの記事を書いている僕自身も、新人看護師時代は夜勤が本当につらくて、心が折れそうになった経験が何度もあるんです。



こんにちは、現役看護師+Webライターの「さくと」と申します。
僕は、とある病院で副看護師長をしながら、毎年やってくる新人さんの教育サポートをしています。
このブログでは、10年以上新人看護師の教育に携わってきた僕の経験から、皆さんの悩みを解決できるような情報を発信しています!
この記事では、そんな僕の体験談や、看護管理者として多くの新人さんを見てきた視点も交えながら、あなたの悩みに寄り添っていきます。
- なぜ新人の夜勤が特にきついのか、そのリアルな理由
- 今日から試せる!きつい夜勤を乗り切るための具体的な10のコツ
- 「もうダメかも…」限界を感じる前に知っておきたい考え方と選択肢
この記事の結論は、「夜勤の“きつさ”は工夫次第で必ず和らげられるし、あなたは決して一人じゃない」ということです。
なぜなら、ここには精神論だけではない、僕自身のたくさんの失敗から学んだ実践的なノウハウや、管理者として「もっと早く教えてあげたかった」と感じる情報が詰まっているから。教科書には載っていない、リアルな現場の声をお届けします!
慣れない環境での緊張感、少ない人数での責任の重さ、そして不規則な生活…。本当に大変ですよね。
でも、安心してください。 この記事を読むことで、漠然とした夜勤への不安が「こうすればいいんだ!」という具体的な対策に変わり、少しでも前向きな気持ちで日々の業務に向き合えるようになるはず。あなたの心と体が、少しでも軽くなる。そんなヒントがきっと見つかります。
少し長い記事ですが、あなたの悩みに寄り添う情報をたくさん詰め込みました。ぜひ目次も活用しながら、気になるところから読んでみてくださいね。
「夜勤きつい…」と感じるのはあなただけじゃない。新人が特に辛い理由



「夜勤、想像以上にきつい…」
「こんなに疲れるなんて…」
新人看護師として働き始め、初めての夜勤を経験して、今まさにそう感じているかもしれませんね。
結論から言うと、新人看護師さんが夜勤を「きつい」と感じるのは、決してあなただけではありません。むしろ、多くの新人が最初にぶつかる大きな壁と言えるでしょう。



では、なぜ特に新人看護師にとって夜勤はこれほどまでに辛いのでしょうか? その理由は、大きく分けて4つの側面と、女性特有の悩みがあります。一つずつ見ていきましょう。
身体的な辛さ:生活リズムの乱れと慢性的な睡眠不足
まず挙げられるのが、身体的な辛さ、特に生活リズムの乱れとそれに伴う慢性的な睡眠不足です。これは、夜勤の“きつさ”の根幹とも言える部分。
僕たちの体には、本来、昼に活動し夜に休息するという約24時間周期の体内時計(サーカディアンリズム)が備わっています。太陽の光を浴びて目覚め、夜暗くなると眠くなる。これが自然なリズムです。 しかし、夜勤はこの自然なリズムに逆行する働き方。体が「休むべき時間」に活動し、「活動すべき時間」に眠ろうとするため、どうしても様々な不調が出やすくなります。
- 寝たいのに眠れない: 夜勤明け、明るい時間に無理に寝ようとしても、寝つきが悪かったり、眠りが浅かったり。
- 日中に強い眠気: 本来頭が冴えているハズの日勤でも、ぼーっとしてしまったり、集中力が続かなかったり。
- 疲労感が抜けない: どれだけ寝ても疲れが取れない、常に体が重い感覚。
- 免疫力の低下: 風邪をひきやすくなったり、体調を崩しやすくなったりすることも。



僕自身も新人時代、夜勤中の深夜2時、3時頃になると、患者さんの記録を書いている最中に、強烈な眠気に襲われていました。意識が遠のいて、パソコンの前でカクン、と船を漕いでしまうことも一度や二度ではありません。「少しだけ目を閉じてもいいですか…?」なんて先輩にお願いしたこともありましたね。



「でも、夜勤は看護師の仕事の一部だし、みんなやってるんだから慣れるんじゃないの?」
と思うかもしれません。 確かに、経験と共に夜勤への「慣れ」は出てきます。しかし、身体への負担が完全になくなるわけではないんです。だからこそ、自分の体をいたわり、意識的にケアしていく必要があります。
身体的な辛さは、目に見えにくいけれど確実に蓄積していくもの。これがまず、夜勤がきつい大きな理由の一つなのです。
精神的な辛さ:少ない人数でのプレッシャーと急変への恐怖
次に、精神的な辛さも大きな要因です。特に、日勤帯に比べて少ない人数で対応しなければならないプレッシャー、そして患者さんの急変に対する恐怖は、新人の心を重くします。
夜勤帯は、日勤帯よりも看護師の配置人数が少ないのが一般的。これは、夜間は緊急入院や検査などが少なく、患者さんも就寝している時間が長いためですが、それでも患者さんの状態が常に安定しているとは限りません。
それが急性期病棟であればなおさら。僕は現在ICUで勤務しているのですが、患者さんの状態は刻々と変化します。1時間前の状況と今の状況が大きく変わっている、なんてこともしょっちゅう。そんな中で経験の少ない新人さんが夜勤をしていると思うと、気が休まらないのもわかります。
- 少ない人数での責任
-
何かあった時、自分が的確に判断し、行動しなければならない場面が増える。
「これで合ってるかな…」「私が見落としていたらどうしよう…」そんなプレッシャーが常につきまとう。 - 相談相手が限られる
-
すぐ隣に頼れる先輩がたくさんいる日勤帯とは違い、相談できる相手が限られる。
仮眠中の先輩を起こすべきか迷ったり、医師への報告をためらったり…。 - 急変への恐怖
-
患者さんの状態が予期せず悪化する「急変」は、いつ起こるか分からない。
特に夜間は、応援を呼ぶにも時間がかかる場合があり、「もし今、急変が起きたら…」という不安は、経験の浅い新人にとっては非常に大きなストレス。



忘れもしません。僕も新人の頃、先輩が仮眠休憩に入っているまさにその時、受け持ちの患者さんの容態が急変したことがありました。モニターのアラームが鳴り響き、頭の中は真っ白。「どうしよう、どうしよう!」と焦るばかりで、緊急時のドクターコールも、しどろもどろになってしまって…。幸い大事には至りませんでしたが、あの時の心臓がバクバクする音と、手の震えは、今でもはっきりと思い出せます。



「でも、緊急時の対応マニュアルもあるし、最終的には医師や先輩が助けてくれるんでしょ?」
と思われるかもしれませんね。 もちろん、どの病院もサポート体制はあります。しかし、最初に患者さんの異変に気づき、行動を起こすのは、多くの場合、担当している自分自身です。その瞬間のプレッシャーと責任感は、言葉で言い表すのが難しいほど重いものなんです。
このように、少ない人数体制の中で求められる判断力と、いつ起こるか分からない急変への恐怖。これらが、精神的なキツさの大きな原因となっています。
環境的な辛さ:慣れない環境と人間関係のストレス
三つ目は、夜勤特有の環境や、人間関係からくるストレスです。これも新人にとっては見過ごせない辛さ。
まず、夜の病院という環境。日中の喧騒が嘘のように静まり返り、薄暗い廊下を一人で歩いていると、なんだか心細い気持ちになったりしませんか?些細な物音にもドキッとしたり。慣れないうちは、この特有の雰囲気自体がストレスになることもあります。
そして、人間関係。夜勤は日勤と比べ、限られた人数で長時間一緒に過ごすことになります。
- 質問や相談のしにくさ
-
「先輩、忙しそうだな…」「こんな初歩的なこと聞いたら、呆れられるかな…」そう思うと、疑問があってもなかなか声をかけられない。
結果、一人で抱え込んでしまう。 - 同期との関係
-
同じように夜勤で疲弊している同期に、弱音を吐きづらかったり、悩みを共有しても「そうだよね!私も!」で終わってしまい、具体的な解決には繋がらなかったり。
- 人間関係の相性
-
正直なところ、どうしても「苦手だな」と感じる先輩や同僚もいるかもしれません。
日勤なら関わる時間が短くても、夜勤でペアになったりすると、そのストレスは倍増どころではありません。



僕にも経験があります。
ある時、緊急入院の患者さんを受け入れるために、病棟内のベッド移動が必要になったんです。
一人では少し大変だったので、夜勤で一緒だった先輩に「手伝っていただけませんか?」とお願いしたら、「え?それくらい一人でできないの?」と冷たく返されてしまって…。結局、渋々一人で重いベッドを動かしましたが、その時の悔しさや、やりきれない気持ちは忘れられません。
夜勤はその日のメンバーによって、働きやすさや精神的な負担が大きく変わる。これも紛れもない事実です。



「人間関係の悩みなんて、どんな職場にでもあるんじゃない?」
という声も聞こえてきそうです。 おっしゃる通り、人間関係は普遍的な課題です。ただ、夜勤という「少人数」「長時間」「外部との接触が少ない」といった特殊な環境下では、その影響がより凝縮され、強く表れやすい傾向がある、ということは知っておいてほしいポイントです。
慣れない環境と、濃密になりがちな人間関係。これらも新人を苦しめる要因の一つです。
新人ならではの辛さ:知識・技術不足への不安と理想とのギャップ
そして四つ目が、新人看護師だからこそ強く感じる、知識や技術不足への不安、そして理想と現実のギャップです。
看護学校で多くのことを学び、国家試験にも合格した。それでも、実際の臨床現場、特に夜勤という状況では、「本当にこれで大丈夫だろうか?」という不安が常につきまといます。
- 判断への自信のなさ
-
患者さんの訴えや観察したことから、「これは緊急性が高いのか?」「もう少し様子を見ていいのか?」その判断に自信が持てない。
- アセスメント・手技への不安
-
「このアセスメントで合ってる?」「点滴のルート確保、失敗したらどうしよう…」一つ一つのケアに時間がかかったり、不安を感じたりする。
- 常に感じるプレッシャー
-
「ちゃんとできているだろうか」「先輩や患者さんに迷惑をかけていないだろうか」周りの目が気になり、常に評価されているようなプレッシャーを感じてしまう。
- 理想とのギャップ
-
看護師になる前に思い描いていた理想の姿と、目の前の必死な自分とのギャップに落ち込んでしまうことも。「もっとテキパキできるはずだったのに…」



これも僕の苦い思い出ですが、夜勤は日勤よりも一人の看護師が受け持つ患者さんの人数が多くなる場合がほとんどです。
新人時代、夜勤終盤の慌ただしい時間帯。朝のケア、バイタルサイン測定、記録、配薬準備…と、多重業務をうまくさばけず、完全にパニックになってしまったことがあるんです。結局、見かねた先輩が駆けつけて手伝ってくれて、ただただ「すみません…」と謝ることしかできませんでした。
あの時の情けなさと申し訳なさは、今でも胸がチクリと痛みます。



「でも、知識や技術は経験を積めば自然と身についていくものでしょう?」
そう考えるひともいるでしょう。 それは間違いありません。日々の経験は、何よりの学びとなり必ずあなたの力になります。でも、その成長過程で感じる不安や焦り、自信のなさは、今この瞬間のあなたにとっては、とてもリアルで重たいもののはずです。その気持ちに蓋をする必要はありません。
経験が浅いからこその不安と、理想通りにいかない現実。これも、新人時代の夜勤が“きつい”、大きな理由なんです。
【コラム】女性看護師特有の悩み(生理周期と体調など )
ここで少し、女性看護師さん特有の悩みについて触れておきたいと思います。 (この記事を書いている僕は男性ですが、長年、多くの女性看護師さんと一緒に働き、管理者としてスタッフの相談に乗る中で見聞きしてきたことです。)
女性の場合、生理周期に伴うホルモンバランスの変化が、心身の調子に大きく影響することがありますよね。
- PMS(月経前症候群): イライラしたり、気分が落ち込んだり、眠気が強くなったり。
- 生理痛: 下腹部痛や腰痛で、業務に集中するのが辛い。
- 貧血: 生理中の出血により、立ちくらみや倦怠感を感じやすい。
ただでさえ大変なこれらの症状が、不規則な夜勤生活によって、さらにコントロールしにくくなったり、症状が悪化したりするケースは少なくないようです。「夜勤が続くと生理不順になりやすい」「肌荒れがひどくなる」といった声もよく聞きます。
これは、生活リズムの乱れがホルモンバランスに影響を与えやすいことや、夜勤による睡眠不足、ストレスなどが複合的に作用するためと考えられます。



男性の僕には、その辛さを完全には理解できないかもしれません。
もし、あなたがこうした女性特有の体調不良で悩んでいるなら、決して一人で我慢しないでくださいね。信頼できる同僚や先輩に話してみるのもいいですし、症状が続くようなら、婦人科を受診したり、上司(師長など)に相談して勤務調整を検討してもらったりすることも考えてみてください。
あなたの体が一番大切ですよ!
「この辛さ、いつまで続くの?」夜勤への“慣れ”と成長について先輩が語るリアル



「夜勤、本当につらい…。このしんどさって、一体いつまで続くんだろう…?」
「先輩たちは普通にこなしてるけど、私もいつかあんな風に”慣れる”日が来るのかな…?」
夜勤の辛さを身をもって感じている今、そんな風に先の見えない不安を抱えているかもしれませんね。



ここでは、誰もが気になる夜勤への「慣れ」と、その先にある「成長」について、僕の経験も踏まえながら、リアルなところをお話ししたいと思います。
夜勤に「慣れる」ってどういうこと? 個人差と時間の経過
まず、夜勤に「慣れる」ということは、確かにあります。でも、それは決して「辛さが完全にゼロになる」という意味ではない、ということを最初に伝えておきたいです。
じゃあ、「慣れる」って具体的にどういうことかというと、
- 時間の使い方が上手くなる
-
夜勤中の業務の優先順位付けや、効率的な動き方が身についてくる。
仮眠や休憩の取り方も自分なりに掴めてくる。 - 精神的に少しタフになる
-
最初はドキドキしていた業務や、ちょっとした出来事に、以前ほど動じなくなる。
いい意味で「こんなものか」と割り切れる部分も出てくる。 - 体のリズムがある程度適応してくる
-
夜勤明けの寝つきが少し良くなったり、日中の眠気が多少コントロールできるようになったり。
体が夜勤モードに切り替わりやすくなる感覚。
とはいえ、これは本当に個人差が大きいんです。数ヶ月で「だいぶ楽になった」と感じる人もいれば、1年経っても「やっぱり夜勤は苦手…」という人もいます。体力的な個人差もあれば、元々の生活リズム、ホルモンバランス、性格なども影響するでしょう。



僕自身も、正直に言うと「夜勤に完全に慣れた!もう全然平気!」とは、15年以上経った今でも言えません。
新人の頃のような絶望的な辛さや、毎回「行きたくない…」と強く思うことはなくなりましたが、やっぱり体は正直で、夜勤が続くと疲労は溜まりますし、夜勤前は「よし、頑張るぞ」と少し気合を入れる感覚はありますよ。



「えー、じゃあ結局、ずっと辛いままってこと…?」
そんな風にがっかりさせてしまったらすみません。でも、そうではありません。 辛さの種類が変わってくる、と言った方が近いかもしれませんね。経験を積むことで、以前は大きなストレスだったことが、乗り越えられるハードルに変わっていく。それが「慣れ」の一つの側面だと思います。
だから、焦って「早く慣れなきゃ!」と思う必要はありません。あなたのペースで、少しずつ夜勤という働き方に体と心を合わせていく。そのくらいの気持ちで大丈夫ですよ。
スキルアップが自信に繋がる! 経験が不安を和らげる側面
夜勤は確かにきつい。でも、その経験は、間違いなくあなたを看護師として大きく成長させてくれます。そして、その成長が自信となり結果的に夜勤への不安を和らげてくれる、というポジティブな側面もあるんです。
なぜなら、夜勤には日勤とは違うスキルアップの機会がたくさん転がっているから。
- 判断力・応用力が鍛えられる
-
先ほどもお話ししたように、夜勤は少ない人数で対応する場面が多いです。だからこそ、自分で考えて判断し、応用力を利かせて動く必要が出てきます。
この経験は、確実にあなたの臨床判断能力を高めてくれるハズ。 - 多重業務への対応力が身につく
-
朝方の慌ただしい時間帯など、限られた時間と人数の中で、複数の業務を同時にこなさなければならない場面も。最初はパニックになるかもしれませんが(僕もそうでした!)、繰り返すうちに、優先順位をつけて効率的に動くスキルが自然と身についてきます。
- 急変対応などの経験値が上がる
-
不安の種である急変対応も、一度経験すると(もちろん、最初は先輩のサポートがあってこそですが)、次に同じような場面に遭遇した時の動きが全く違ってきます。
「あの時はこうだったから、次はこうしよう」と、冷静に対応できる部分が増えていく。失敗も含めて、全ての経験があなたの貴重な財産になるんです。 - 患者さんの全体像を把握する力がつく
-
夜間の静かな時間に、患者さんの日中の記録をじっくり読み込んだり、患者さんと少し長く話したりする中で、その人となりや病状の全体像を深く理解できることもあります。
これは日勤の忙しさの中では得難い経験かもしれません。



僕自身、受け持ち患者さんの全体像を把握する力や、予測して動く力は、夜勤業務を通して特に鍛えられたな、と感じています。



「でも、今は辛すぎて、成長なんて考えられない…」
その気持ち、すごくよく分かります。今は目の前の業務をこなすことで精一杯。自分の成長なんて、とても考えられる状況じゃないですよね。
でも、ちょっとだけ想像してみてください。数ヶ月後、あるいは一年後のあなたは、今よりも確実にできることが増え、自信を持って患者さんの前に立てているはずです。今の辛い経験の一つ一つが、未来のあなたを作るための大切なピースになっている。そう信じてみてください。
でも無理は禁物! 心と体のサインを見逃さないで
ここまで「慣れ」や「成長」といった前向きな側面についてお話ししてきましたが、最後に、一番大切なことを伝えます。それは、絶対に無理はしないでほしい、ということです。
慣れることも成長することも、もちろん大切。でも、それはあなたの心と体が健康であってこそです。頑張りすぎて心や体を壊してしまっては、元も子もありません。
看護師は、人の命と健康を守る仕事。だからこそ、自分自身の心と体の健康にも、もっと敏感になってほしいんです。
特に注意したいのが、バーンアウト(燃え尽き症候群)。強い使命感や責任感から、自分の限界を超えて頑張り続けてしまうことで、ある日とつぜん心身のエネルギーが枯渇し、無気力になってしまう状態です。
そうならないために、自分の心と体が発している「SOSサイン」を見逃さないでください。
- なかなか寝付けない、夜中に何度も目が覚める、早く目が覚めすぎる
- 食欲が全くない、または逆に食べ過ぎてしまう
- 原因不明の頭痛、めまい、動悸、腹痛などが続く
- 仕事に行こうとすると涙が出る、気分がひどく落ち込む
- 今まで好きだったことや、楽しめていたことに興味が持てなくなった
- ケアレスミスが増えたり、集中力が続かなくなったりする



僕自身は、体調を崩しやすくなる程度の不調で済みましたが、中には無理がたたって体調を崩し、しばらく休職したスタッフを見たことがあります。
その人は「自分が休んだら周りに迷惑がかかる」と、不調を感じながらも頑張っていました。その頃は僕も経験が浅かったので、話を聞くぐらいしかできませんでした。
でも、今なら分かります。休むことも自分を守ることも、大切な仕事の一部なんです。
今では管理者として、スタッフが無理をしていないか、表情や言動に変化はないか、常にアンテナを張るように心がけています。
もし、上に挙げたようなサインが続いているなら、それはあなたの心と体が「もう限界だよ」と訴えている証拠かもしれません。 「まだ大丈夫」「気のせいだ」と思わずに、自分の限界を認め、早めに対処すること。それが、あなたが看護師として長く健康に働き続けるために、何よりも大切なことですよ。
夜勤への「慣れ」は確かにありますが、個人差が大きく、無理は禁物です。 しかし、その過程で得られる経験は、必ずあなたの成長と自信に繋がります。 大切なのは、自分の心と体の声に耳を傾け、自分のペースで進んでいくこと。
【管理者直伝】きつい夜勤を乗り切るための具体的な10のコツ
さて、ここからはいよいよ本題! 「夜勤がきつい…」その辛さを少しでも和らげるために、今日から、いや今からでも試せる具体的なコツを、僕自身の経験や管理者として見てきた工夫も交えながら、10個に厳選してお伝えします。



全部を一気にやろうとしなくて大丈夫。「これならできそうかも」と思うものから、ぜひ試してみてくださいね!
※気になるコツを選ぶと、対応したところに飛べますよ!
<夜勤前>質の高い仮眠をとる工夫
まず、夜勤前の仮眠はめちゃくちゃ重要です。特に、これが夜勤中のパフォーマンスや体調を大きく左右すると言っても過言ではありません。
ただ、一言で「夜勤前の仮眠」と言っても、皆さんの勤務形態(2交代制か3交代制か)によって、意識すべきポイントが少し変わってきます。 僕も両方の勤務を経験しているので、それぞれのパターンに分けて工夫のコツをお話ししますね。
【2交代制の場合】夜勤中の仮眠の質を高めるための「夜勤前」の過ごし方
2交代制の場合、多くは夜勤中に数時間の仮眠時間が設けられていますよね。(もちろん、忙しくて全く取れない!なんて日もありますが…) この夜勤中の仮眠の質を最大限に高めるために、実は「夜勤に入る前の日中」の過ごし方がポイントになるんです。



「夜勤前だから、昼までゆっくり寝て体力を温存しよう!」
「前日は夜更かしして、昼間たっぷり寝ておけば夜勤も大丈夫でしょ?」
…もし、あなたがこんな風に考えていたら、ちょっと待った! 実はこれ、逆効果になってしまうことがあるんです。
なぜなら?
前日に夜更かししたり、昼過ぎまで寝てしまったりすると、体内時計が大きく乱れてしまいます。その結果、いざ夜勤中の仮眠時間になっても「目が冴えてしまって全然眠れない…」なんてことになりかねません。これでは、せっかくの仮眠時間が無駄になってしまいますよね。



じゃあ、どうすればいいか? 僕が個人的に試して「これは効果があったな」と感じているのは、「いつも通りの時間に起きて、昼食後に仮眠をとる」という方法です。
- 朝は普段通りか、少し遅めに起きる(昼まで寝ない!)
- 午前中は普通に過ごす(買い物に行ったり、軽く家事をしたり)
- 昼食をとった後、14時~16時くらいの間で、1時間半~2時間程度の仮眠をとる
こうすることで、生活リズムの大きな乱れを防ぎつつ、夜勤に向けてのエネルギーをチャージできるんです。夜勤中の仮眠も、比較的スムーズにとれるようになりました。
もちろん、これはあくまで僕個人の経験なので、全ての人に当てはまるかは分かりません。でも、「夜勤中の仮眠がなかなか上手くとれない…」と悩んでいるなら、一度、夜勤前の「昼寝スタイル」を見直してみるのは試す価値アリだと思いますよ。
【3交代制の場合】短時間でも効果的に!「夜勤前」仮眠の工夫
一方、3交代制、特に日勤が終わってから数時間後には夜勤が始まる…といったシフトの場合、夜勤中にまとまった仮眠時間を確保するのは難しいことが多いですよね。 そうなると、夜勤に入る前の「短い時間」で、いかに質の高い仮眠をとるかが勝負になります。
日勤が終わって家に帰り、夕食をとり、お風呂に入り、出勤の準備をして…となると、仮眠にあてられる時間は本当にわずか。「もう、いっそ寝ない方が楽かも…」なんて思う気持ちも分かります。
でも、たとえ30分でも、15分でもいい。少しでも目を閉じて脳を休ませることは、その後の夜勤を乗り切る上で大きな助けになります。



限られた時間で質の高い仮眠をとるための、僕からのおすすめは「シャワーで済ませず、湯船に浸かる」こと。
なぜなら?
入浴には、一時的に深部体温を上げ、その後、体温が下がる過程で自然な眠気を誘う効果があると言われているからです(※)。いわば、体の「おやすみスイッチ」を入れてくれる感覚ですね。もちろん、リラックス効果も期待できます。
※出典:厚生労働省 e-ヘルスネット「快眠と生活習慣」などを参考にしています。
ただし!ここで最大の注意点は「寝過ごし」です。 お風呂に入ってリラックスし、ウトウト…そのまま深い眠りに…気づいたら出勤時間ギリギリ!…いや、もう遅刻だ! なんてことになったら目も当てられません。



これは本当に、僕自身が新人の頃にやらかした失敗談なのですが…日勤後に疲れて帰宅し、お風呂に入って仮眠をとったんです。目覚ましはかけたハズなのに、全く気づかず…。
結局、病院からの着信音で飛び起きました。あの時の冷や汗と、病棟に駆け込んだ時の先輩方の視線は、一生忘れられません…。
なので、
- 目覚まし(アラーム)は絶対にセットする! しかも、複数かける、音量を最大にする、バイブレーションもONにするなど、確実に起きられる工夫をしてください。
- スマホのアラームだけでなく、目覚まし時計も併用すると、より安心かもしれません。
- 家族がいるなら、「〇時に起こして!」とお願いしておくのも手ですね。
3交代制の夜勤前仮眠は、時間との戦い。短時間でも効果を最大化する工夫と、絶対に寝過ごさないための対策。この両輪が大切になります。
(共通の工夫)寝室の環境を整える
そして、2交代制でも3交代制でも共通して大切なのが、仮眠をとる際の「環境」です。
- 光を遮断する: 遮光カーテン、アイマスクを活用!
- 音を遮断する: 耳栓、静かな環境づくり!
- 快適な温度・湿度: 自分に合った設定を!
質の高い睡眠のためには、やはり環境づくりが基本になりますね。
夜勤前の仮眠、あなたの勤務スタイルに合わせて、少し工夫を取り入れてみてください。きっと、夜勤中の辛さが少し和らぐはずですよ。
<夜勤前>食事は消化の良いものを、カフェイン摂取のタイミング
夜勤前の食事も、実はパフォーマンスに影響します。ポイントは「消化の良いもの」を「適切なタイミング」でとること。
なぜなら?
胃腸に負担のかかる食事は、眠気を誘発したり、夜勤中の胃もたれの原因になったりするからです。また、カフェインはタイミングが重要。
- 避けた方が良いもの: 揚げ物、脂っこい肉料理、香辛料の強いもの、食べ放題など(消化に時間がかかり、負担が大きい)。
- おすすめ: うどん、おかゆ、スープ、豆腐、白身魚、鶏むね肉、バナナなど(消化が良く、エネルギーになりやすい)。
「夜勤前は食欲がなくて…」という時もありますよね。そんな時は無理に固形物を食べなくても大丈夫。栄養のあるスープやゼリー飲料、バナナなどで軽くエネルギー補給するだけでも違いますよ。
<夜勤中>眠気対策の小ワザ集
さあ、いよいよ夜勤本番。どんなに準備しても、魔の時間帯(深夜2時~明け方)には強烈な眠気が襲ってくることも…。そんな時のために、眠気を吹き飛ばす小ワザをいくつか持っておくと心強いです。
なぜなら?
眠気は集中力低下やミスの原因に直結します。患者さんの安全を守るためにも、自分自身のパフォーマンスを維持するためにも、眠気対策は必須!
ラウンドの合間に屈伸したり、肩を回したり。少し血行を良くするだけでも気分転換になります。階段の上り下りも効果的。



【最終手段?】先輩に相談する
どうしても眠気が限界な時…僕も新人の頃、勇気を出して「すみません、少しだけ目を閉じてもいいですか…?」と先輩にお願いしたことがあります。
もちろん状況によりますが、安全に業務を続けるために、正直に伝えることも時には必要かもしれません。(ただし、まずは自分でできる対策を試しましょう!)



「眠気覚ましのドリンクに頼っちゃダメかな?」
もちろん、カフェイン飲料なども有効な手段の一つです。ただ、頼りすぎると効果が薄れたり、体への負担になったりすることも。これらの小ワザと上手く組み合わせて、乗り切るのがベストですね。
<夜勤中>集中力を保つための業務の進め方
夜勤中は判断力が鈍ったり、うっかりミスが増えたりしがち。集中力を保ち、安全に業務を進めるための工夫も大切です。
なぜなら?
夜勤中のミスは、患者さんの安全に直結する可能性があります。限られた人数の中で効率よく、かつ確実に業務をこなす必要があるからです。
- その日の夜勤で「必ずやること」「時間があればやること」をリストアップする。
- 緊急度と重要度を考えて、優先順位を明確にする。「今すぐやるべきこと」は何かを常に意識する。



「新人だから、優先順位なんてまだよく分からない…」
最初はそれで当然です!分からないこと、判断に迷うことは、必ず先輩に確認・相談しましょう。「念のため確認させてください」という姿勢は、決して悪いことではありません。むしろ、安全意識が高い証拠ですよ。
<夜勤中>効果的な休憩・仮眠の取り方
夜勤中の休憩や仮眠は、疲労回復と集中力維持のために非常に重要です。たとえ短い時間でも、質の高い休息をとることを意識しましょう。
なぜなら?
適切な休息は、後半の業務のパフォーマンスを高め、ミスを防ぐことに繋がります。心身のリフレッシュにも不可欠。
- 15分~30分程度の短い仮眠でも、脳の疲労回復には大きな効果があります(※)。
深い眠りに入る前に起きるのがポイント。 - アラームをセットするのを忘れずに!
※出典:労働者健康安全機構「睡眠障害の基礎知識」などを参考にしています。



「うちの病院、仮眠時間なんてほとんど取れないんだけど…」
そういった厳しい環境もあるかもしれませんね…。それでも、5分でも10分でも、意識的に休憩を取るように心がけてみてください。目を閉じて深呼吸するだけでも違います。自分の心身を守るために、できる範囲で休息を確保する工夫が大切です。
<夜勤明け>体内時計リセット術
夜勤が終わった!…と解放感に浸りたいところですが、夜勤明けの過ごし方が、次の勤務や体調に大きく影響します。ポイントは体内時計をリセットすること。
なぜなら?
夜勤でズレてしまった体内時計を、できるだけ早く通常の昼夜リズムに戻すことが、睡眠の質を高め疲労回復を促す鍵となるからです。
- 夜勤明け、帰宅時に意識して太陽の光(特に朝日)を浴びましょう。たとえ曇り空でも光は届いています。サングラスはできれば外して。
- 光を浴びることで、体内時計に「朝だよ!」と知らせ、メラトニン(睡眠ホルモン)の分泌を抑制し、覚醒を促します。



「夜勤明けは、とにかくすぐ寝たいんだけど…」
その気持ち、すごくよく分かります!でも、ほんの少しだけ朝日を浴びる、何か軽く口にする、という一手間を加えるだけで、その後の睡眠の質や翌日の体調が変わってくる可能性があります。ぜひ試してみてください。
<夜勤明け>疲労回復を最優先する過ごし方
体内時計をリセットしたら、次はいよいよ質の高い睡眠をとって、しっかりと疲労回復に努めましょう。
なぜなら?
夜勤による心身の疲労は想像以上。ここでしっかり回復できるかが、次の勤務への活力や、長期的な健康維持に繋がるからです。
- <夜勤前>の仮眠と同様、暗く、静かで、快適な温度・湿度の寝室を用意する。
僕はマットレスや枕など、寝具にこだわるようにしています!
※出典:在宅照明中のブルーライトが体内時計と睡眠覚醒に与える影響



【体験談】帰宅時の注意!
これは僕の苦い経験ですが…夜勤明けの運転は本当に危険です!強烈な眠気に襲われて、コンビニの駐車場で仮眠をとってから帰ったことが何度もあります。
車通勤の方は、少しでも眠気を感じたら絶対に無理せず、仮眠をとるか、公共交通機関の利用なども検討してくださいね。
夜勤明けは、家事などを頑張りすぎず、「今日は体を休める日!」と割り切ることも大切ですよ。
<日頃から>ストレスを溜めない工夫
夜勤の辛さは、身体的なものだけではありません。精神的なストレスも大きいですよね。だからこそ、日頃からストレスを上手に発散し、溜め込まない工夫が重要になります。
なぜなら?
ストレスが溜まると、不眠や食欲不振、気分の落ち込みなどを引き起こし、さらに夜勤を辛くさせてしまう悪循環に陥る可能性があるからです。
- 「これをすると気分がスッキリする!」という方法をいくつか持っておきましょう。人によって様々です。
- 例:好きな音楽を聴く、映画を見る、読書をする、美味しいものを食べる、友人と話す、カラオケに行く、運動する、自然に触れる、アロマを焚く、ゆっくりお風呂に入る、ペットと遊ぶ、何もしないでボーっとする…など。
ストレス解消法は、一つだけでなく複数持っておくのがおすすめです。その時の気分や状況に合わせて使い分けられると、より効果的ですよ。
<日頃から>体力づくりのための軽い運動習慣



「夜勤を乗り切るには、やっぱり体力も必要?」
ある程度の体力は、夜勤という不規則な勤務を乗り切る上で助けになります。日頃から無理のない範囲で運動習慣を取り入れてみましょう。
なぜなら?
適度な運動は、体力向上だけでなく、ストレス解消、睡眠の質の向上、生活リズムの調整にも繋がるからです。
- 大切なのは「継続すること」。ハードなトレーニングではなく、自分が心地よく続けられる運動を選びましょう。



「疲れてるのに運動なんて…」
と思うかもしれません。でも、軽い運動は逆に疲労回復を促す効果もあるんです。だまされたと思って、まずは5分・10分のウォーキングから始めてみませんか? きっと気分もスッキリしますよ。
<日頃から>頼れる「夜勤のお供」を見つける
最後は、ちょっとした「お守り」のような存在、あなただけの「夜勤のお供」を見つけることです。
なぜなら?
辛い夜勤中に、ほんの少しでも「ホッ」とできたり、「頑張ろう」と思えたりするアイテムや習慣があると、精神的な支えになるからです。
- 温かいハーブティー(カモミールやペパーミントなど、リラックス効果のあるもの)、好きな味のインスタントスープ、ちょっと贅沢なコーヒーや紅茶など。休憩タイムに飲む人は意外と多いですよ!
これはほんの一例です。あなたにとって「これがあると少し頑張れる」「ちょっと気分が上がる」ものは何でしょうか? 高価なものである必要はありません。自分だけのささやかな「お供」を見つけて、辛い夜勤を乗り切る味方にしてくださいね。



以上、きつい夜勤を乗り切るための具体的な10個のコツをご紹介しました。 どれも特別なことではありませんが、意識して取り入れることで、あなたの夜勤が少しでも楽になることを願っています。
ちょっと視点を変えてみる? 夜勤だからこそのメリット
ここまで、夜勤の「きつさ」や、それをどう乗り越えるか、という話を中心にしてきました。
「やっぱり夜勤って大変なんだな…」と感じているかもしれませんね。
でも、ちょっとだけ視点を変えてみると、夜勤には夜勤ならではの「メリット」もあるんです。 もちろん、“きつい”ことに変わりはないけれど、少しでもポジティブな側面を知っておくと、夜勤に対する気持ちがほんの少し変わるかもしれませんよ。



「メリットなんてあるの?」
と思うかもしれませんが、意外と見逃せないポイントが3つあります。
平日の昼間を有効活用できる
まず一つ目のメリットは、平日の昼間を自由に使える時間が増えることです。これは、夜勤ならではの大きな魅力と言えるでしょう。
なぜなら?
多くの人が働いたり、学校に行ったりしている時間帯に“自分は休み”、という状況が生まれるからです。
| 役所や銀行での手続きがスムーズ | 平日昼間しか開いていない窓口での用事を、わざわざ休みを取らなくても済ませられます。 あの混雑や待ち時間から解放されるのは嬉しいですよね。 |
|---|---|
| 人気のカフェやお店をゆっくり楽しめる | 土日は混雑しているような話題のお店も、平日なら比較的空いていて、ゆっくりと過ごせる可能性が高いです。 |
| 病院や美容院の予約が取りやすい | 平日昼間の予約枠は、土日に比べて取りやすいことが多いです。 |
| 通勤・移動ラッシュを避けられる | 夜勤の入りや明けの時間は、一般的な通勤ラッシュとズレていることが多いので、満員電車や道路の渋滞といったストレスが少ないのもメリット。 |



僕自身、夜勤明けに一度しっかり仮眠をとって、夕方からゆっくり買い物に出かけたり、ちょっと美味しいものを食べに行ったりするのが好きなんです。
平日の空いている時間に自分の用事を済ませられると、「得したな!」という気分になりますよ。



「でも、夜勤明けは疲れて結局寝ているだけで、何もできないんだけど…」
その気持ち、よーく分かります!僕も新人の頃はそうでした。でも、この記事で紹介しているような体調管理のコツを掴んでいくと、意外と夜勤明けでも活動できる時間が生まれてくるんです。もちろん無理は禁物ですが、「今日は少し外に出てみようかな」くらいの軽い気持ちで、平日の昼間時間を楽しむことを考えてみるのも良いかもしれませんね。
夜勤手当で収入アップ
二つ目のメリットは、やはり収入面でのプラスが大きいことです。頑張った分が、目に見える形で返ってくるのは嬉しいものですよね。
なぜなら?
法律で定められた割増賃金や、病院独自の夜勤手当が支給されるため、日勤のみの場合よりも給与が高くなる傾向があるからです。
| 深夜割増賃金(深夜手当) | 法律(労働基準法 第37条)で、午後10時から午前5時までの間に働いた場合、通常の賃金の25%(2割5分)以上の割増賃金を支払うことが義務付けられています。これはどの病院でも必ず支払われるものです。 |
|---|---|
| 夜勤手当 | 上記の深夜割増賃金とは別に、病院が独自に定めている手当です。「1回の夜勤につき〇〇円」といった形で支給されることが多いですね。この金額は病院によってかなり差があります。 |



僕が今勤めている病院の話ですが、夜勤を専門に行う「夜勤専従」という働き方をすると、通常の夜勤手当に加えて、さらに「専従手当」がプラスされます。夜勤回数も多くなるので、月によっては手取りが普段より5万円以上アップすることも!これはかなり大きなモチベーションになりましたね。



「でも、お金のために体を壊したら意味ないんじゃ…?」
おっしゃる通りです!健康が第一なのは言うまでもありません。ただ、経済的な安定が心の余裕につながることも事実。特に新人時代は、奨学金の返済があったり、一人暮らしを始めたりと、何かとお金が必要な時期でもありますよね。夜勤手当がそうした経済的な面をサポートしてくれるのは、無視できないメリットと言えるでしょう。(もちろん、手当の額は病院によって異なるので、ご自身の給与明細などを確認してみてくださいね!)
少人数体制で主体的に動く経験が積める(判断力・応用力UP)
三つ目のメリットは、一見デメリットにも思える「少人数体制」が、実は看護師としての成長を大きく促してくれるという点です。
なぜなら?
日勤帯のように周りにたくさんの先輩がいる環境とは違い、夜勤中は自分で考えて判断し、主体的に行動しなければならない場面が格段に増えるからです。
| 臨床判断能力が磨かれる | 「この患者さんの状態、報告すべきか?」「このケアは今すぐ必要か?」など、一つ一つの判断を自分でする経験を通して、アセスメント能力や状況判断能力が自然と鍛えられます。 |
|---|---|
| 応用力が身につく | 限られた人手や物品の中で、どうすれば効率よく、安全にケアを提供できるか? 工夫する力が養われます。 |
| 幅広い業務を経験できる | 部署によっては、日勤帯は業務が細分化されていても、夜勤帯は一人の看護師がより幅広い業務を担当することもあります。これにより、看護師としての視野が広がります。 |



これは僕自身の経験ですが、「自分がしっかりしないと、患者さんや他のスタッフに迷惑がかかる!」というプレッシャーは、正直、最初はものすごいストレスでした。
でも、そのプレッシャーがあったからこそ、「もっと勉強しなきゃ」「もっと的確に動けるようにならなきゃ」と必死になれたんです。
そして、少しずつできることが増えてくると、不思議とプレッシャーが自信に変わり、ストレスも軽減していく。そんな感覚を何度も経験しました。



「プレッシャーは嫌だな…成長よりも、今はとにかく楽になりたい…」
その気持ちも痛いほどよく分かります。特に新人時代は、成長なんて考える余裕がないくらい、目の前のことでいっぱいいっぱいですよね。
でも、思い出してください。あの時、必死で乗り越えた経験が、今のあなたの看護師としての土台を作っているはずです。その夜勤での経験は、間違いなくあなたの今後のキャリアにおいて大きな強みになります。「やらざるを得ない」状況が、知らず知らずのうちにあなたをたくましく育ててくれている。そんな風に捉えてみることもできるんですよ。



夜勤は確かに大変ですが、見方を変えればこんなメリットもあるんです。 もちろん、これらのメリットがあるからといって、辛い気持ちを我慢する必要は全くありません。
ただ、“きつい”という側面だけでなく、こうしたポジティブな側面もあることを知っておくと、少しだけ夜勤に対する気持ちが変わるかもしれません。
どうしても辛い…限界を感じる前に試したいこと・相談したいこと
ここまで、夜勤を乗り切るためのコツや、夜勤ならではのメリットについてお話ししてきました。 色々な工夫を試してみることで、少しは気持ちが楽になったり、前向きになれたりするかもしれません。
でも、それでもやっぱり「どうしても辛い…」「もう限界かもしれない…」と感じてしまう時だってありますよね。



そんな時は、絶対に一人で抱え込んで、無理をしすぎないでください。 あなたの心と体が壊れてしまう前に、できること、相談できる相手がきっといます。 限界を感じる前に試してほしいこと、そして相談してほしいことを、順番にお伝えしますね。
まずは一人で抱え込まず、信頼できる人に話してみよう
何よりもまず、一番に伝えたいのは、「一人で抱え込まない」ということです。 辛い気持ち、不安な気持ちを、信頼できる誰かに話してみませんか?
なぜなら?
声に出して話すことで、自分の気持ちが整理されたり、「なんだ、そんなに深刻に悩むことでもなかったかも」と少し客観的になれたりするものです。また、話を聞いてもらって共感してもらうだけでも、孤独感が和らぎ、心が軽くなることがあります。
時には、自分では思いつかなかったアドバイスをもらえることも。
特に、あなたの教育担当であるプリセプターや、あなたが「話しやすいな」と感じる年の近い先輩。同じ道を通ってきたからこそ、あなたの気持ちを理解してくれるはず。具体的なアドバイスは先輩に聞くに限ります!
それぞれに良さがあるので、どんな人にも話できるのが理想ではあります。ですが、特に最初は限られた人だけでも大丈夫。大切なのは、あなたが「この人になら安心して話せる」と思える相手を選ぶことです。



僕も新人の頃は、人見知りだったこともあり「こんなことで悩んでるなんて、情けない」「弱音を吐いたらダメだ」と思い込み、なかなか人に相談できずに一人で悶々としていた時期がありました。
でも、ある時、思い切って信頼する先輩に打ち明けてみたんです。そしたら、「そんなの、お前だけじゃないよ。俺も新人の時、同じことでめちゃくちゃ悩んだもん」と言ってもらえて…。肩の荷がスッと降りて、すごく気持ちが楽になったのを覚えています。「なんだ、みんな同じように悩んで、乗り越えてきてるんだ」って思えて前向きになれたんです。
だから、あなたも一人で抱え込まずに誰かに話をしてみてくださいね!
部署内で相談できることはないか?
辛さの原因が、人間関係や業務内容など、今の部署の環境にあると感じる場合、部署内で改善できる点がないか、相談してみるのも一つの手です。
なぜなら?
自分一人では変えられないことでも、上司や同僚に相談することで、周りが協力してくれたり、改善策が見つかったりする可能性があるからです。「どうせ無理だろう」と諦める前に、一度声を上げてみませんか?
| どんな相談? | 具体的な内容 | “さくと”からひと言 |
|---|---|---|
| 夜勤メンバーの調整 | どうしても苦手な先輩との連続勤務が続いている、相性の悪いスタッフとのペアが多い…など、人間関係が大きなストレスになっている場合、師長に相談してみる。 「少し配慮していただけると助かります」と正直に伝えてみる価値はあります。 | ただ、ここだけの話、管理者によっては口が軽い人もいるので、相談しても大丈夫な管理者かどうか、周りに確認してからの方が良いかも… |
| 業務分担の見直し | 特定の業務(例えば、重症度の高い患者さんの受け持ち、負担の大きい係の仕事など)が、いつも自分に集中しているように感じる場合、業務分担について相談してみる。 | 先輩たちは成長のため、と思って少し負担のかかる仕事を任せている可能性もあります。 期待してくれているのは嬉しいことですが、心が折れてしまっては意味がないので、「ちょっと“きつい”な」と思ったら、一度相談してみましょう。 |
| 休憩・仮眠時間の確保 | 忙しすぎて休憩や仮眠が全く取れない状況が続いている場合、どうすれば休憩時間を確保できるか、チームで話し合ってみる。 「業務を効率化するために、こんな工夫はどうだろう?」といった提案をしてみるのも良いかもしれません。 | 新人のうちから業務について意見をするのはちょっとハードルが高いかもしれません。 が、代わりに提案してくれそうな頼れる先輩がいる場合は相談の価値アリ! 師長は意外に業務の細かいところまでわかっていなかったりするので、師長に相談してみるのも一つかも! |



「そんなこと相談したら、わがままって思われないかな…?」
そう心配になる気持ちも分かります。でも、あなたが安心して、安全に働ける環境を作ることは、部署全体にとっても大切なことなんです。



管理者としての視点から言わせてもらうと、スタッフがどんなことに困っているのか、何にストレスを感じているのかは、できるだけ把握したいと思っています。もちろん、全ての要望に応えられるわけではありませんが、相談してもらえなければ、問題があること自体に気づけないこともあります。
言いにくいことかもしれませんが、勇気を出して相談してくれることは、むしろ部署をより良くしていくための第一歩になるんですよ。
思い切って長期休暇(リフレッシュ休暇)を取得して心身を休める



「もう何も考えられないくらい、心も体も疲れ切ってしまった…」
そんな風に感じているなら、一度、思い切って仕事から離れて、まとまったお休み(長期休暇)をとることを考えてみてください。
なぜなら?
心身が疲弊しきっている状態では、正常な判断もできなくなってしまいます。十分な休息をとることで、エネルギーを再充電し、冷静に自分の状況や今後のことを見つめ直す時間を持つことができます。これは、バーンアウト(燃え尽き症候群)を防ぐためにも非常に有効な手段です。
| 有給休暇を活用する | 溜まっている有給休暇があれば、消化できないか相談してみましょう。数日間まとまって休むだけでも、気分転換になります。 |
|---|---|
| リフレッシュ休暇制度などを確認する | 病院によっては、勤続年数に応じてリフレッシュ休暇などの特別な休暇制度が設けられている場合があります。就業規則などを確認してみましょう。 |
| 休暇中の過ごし方 | 旅行に行って気分転換する、趣味に没頭する、実家に帰ってゆっくり過ごす、あるいは、家でひたすら寝る…など、あなたが一番リラックスできる方法で過ごすのがベストです。「何か有意義なことをしなきゃ」と考える必要はありません。 |



「私が休んだら、病棟が人手不足になって、周りに迷惑がかかるんじゃ…」
その気持ち、責任感の強いあなただからこそ、考えてしまうことだと思います。確かに、あなたが休む間、他のスタッフが業務をカバーしてくれることになります。でも、考えてみてください。あなたが無理を続けて心身を壊してしまい、長期離脱や退職になってしまうことの方が、結果的に職場にとっては大きな損失になるのではないでしょうか?
周りのスタッフも、あなたが元気になって戻ってきてくれることを願っているはずです。休むことは、決して悪いことではありません。むしろ、あなたがこれからも看護師として働き続けるために必要な、大切な権利であり、必要なプロセスなんです。



ただそのためには、職場内での人間関係をきちっと築いておくことも大切!関係性ができていれば、休暇を取ることに周りのスタッフも協力してくれるはずです。
先輩とより良い人間関係を築くためのコツについて▼こちらの記事▼でまとめていますので良ければ見てみてください!
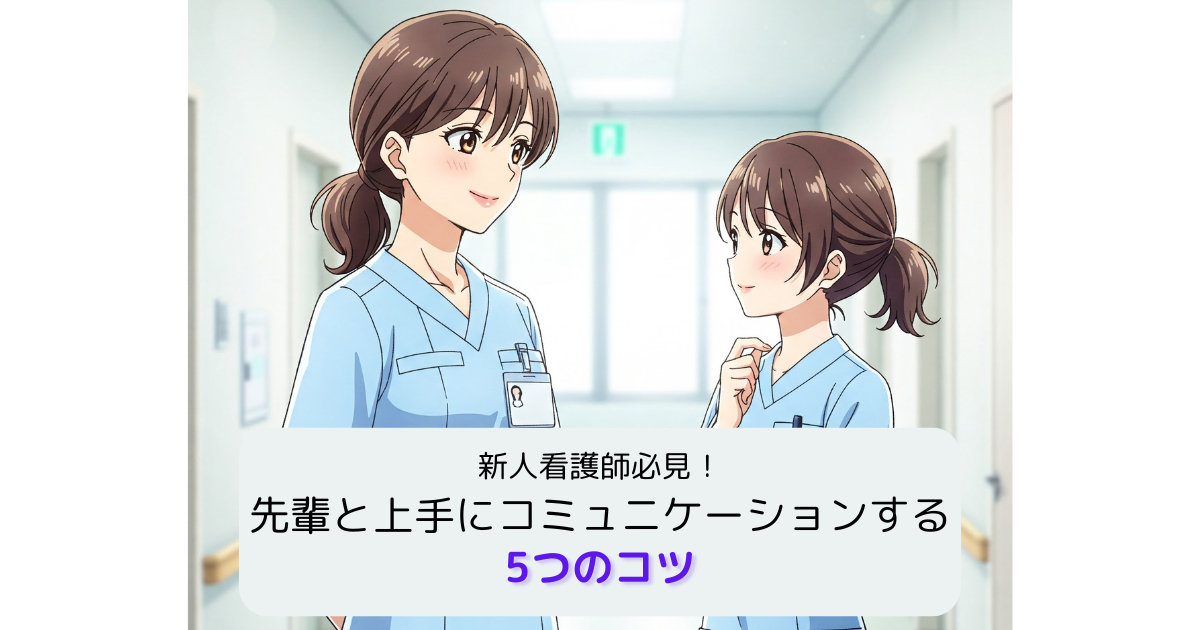
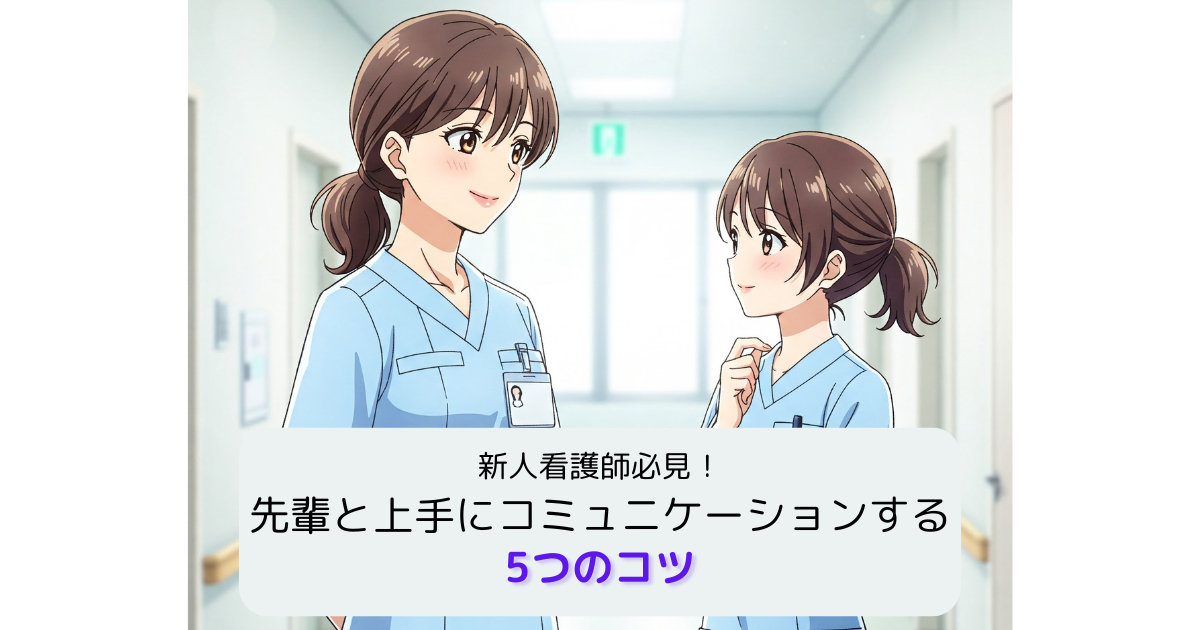
上司や師長に相談して、夜勤回数の調整や部署異動を検討してもらう
様々な工夫をしても、どうしても夜勤自体が身体的・精神的に合わない、辛すぎると感じる場合。それは、働き方そのものを見直すタイミングなのかもしれません。
上司や師長に正直な気持ちを伝え、夜勤回数の調整や、夜勤の負担が少ない部署への異動などを相談してみることも、真剣に考えてみましょう。
なぜなら?
人それぞれ、体力や生活環境、ライフステージは異なります。あなたにとって「無理のない働き方」は、他の人と同じとは限りません。自分に合わない働き方を無理して続ける必要はないんです。
| 夜勤回数の削減 | 例えば、「今は月に8回夜勤に入っていますが、体調的に辛いので、6回程度に減らしていただくことは可能でしょうか?」といった具体的な相談。 |
|---|---|
| 日勤常勤への変更 | 夜勤がどうしても無理な場合、日勤のみの勤務形態に変更できないか相談する。 |
| 部署異動の希望 | 夜勤の負担が比較的少ないとされる部署(例:外来、内視鏡室、手術室、透析室など)への異動を希望する。 |



僕も管理者として、スタッフから「体調的に夜勤が辛い」「家族の状況で、夜勤回数を減らしたい」といった相談を受けた際には、本人の状況を詳しく聞き、可能な範囲で夜勤回数を調整したり、人員状況を見ながら他の部署への異動を一緒に検討したりしてきました。
すぐに希望通りになるとは限りませんが、あなたの健康と、長く働き続けてもらうことが、組織にとっても一番大切だと考えています。
だから、「こんなこと相談したら…」なんて、ためらわないでください。 あなたの正直な気持ちを聞かせてほしいと思っています。
【最後の手段として】どうしても環境が合わない場合は転職も選択肢の一つ
ここまで、現職場でできること、相談できることをお話ししてきました。 まずはこれらの方法を試してみてほしい。心からそう願っています。
でも、もし、



色々な手を尽くしてみたけれど、状況が全く改善しない…
今の職場環境が、どうしても自分には合わない…
心身の限界を超えてしまいそうだ…
そんな風に感じるなら、最後の手段として、「転職」という選択肢も、あなたの未来を守るためには必要になってくるかもしれません。
これは、決して安易に転職を勧めているわけではありません。 新しい環境に移ることが、必ずしも全てを解決するとは限りませんし、転職にはエネルギーも必要です。
ただ、自分に合わない環境で無理をし続け、心身を壊してしまうくらいなら、勇気を出して新しい場所を探す方が、結果的にあなたがあなたらしく、看護師という仕事を長く続けていくことに繋がる場合もある、ということを知っておいてほしいんです。
もし、あなたが「転職」という選択肢を少しでも考え始めたなら…次の章で、夜勤のない働き方や、転職を考える際のヒントについて少し触れていきますね。



辛い時、限界を感じる時は、決して一人で耐えないでください。 話すこと、相談すること、休むこと、そして働き方を見直すこと。 あなたには、たくさんの選択肢があります。
(参考)こういう働き方もある:夜勤なし・日勤のみの職場
前の章で、「最後の手段として転職も…」というお話を少ししました。 ここで紹介するのは、すぐに転職を勧めるためではありません。 あくまで、「もし、どうしても夜勤がきついと感じるなら、世の中にはこういう働き方もあるんだな」という参考情報として、頭の片隅に置いてもらえたら、というものです。



「夜勤のない働き方なんて、本当にあるの?」
「どんな仕事があるんだろう?」
そう思う人もいるかもしれませんね。意外と選択肢は色々あるんですよ。 知っておくだけでも、「いざとなったらこういう道もあるんだ」と、少し気持ちが楽になるかもしれません。
繰り返しになりますが、ここからの情報は「こういう働き方もあるよ」という紹介です。 夜勤がないからといって、必ずしも楽なわけではありません。日勤には日勤の大変さがありますし、給与面など変化する部分もたくさんあります。
それを踏まえた上で、「こんな選択肢もあるんだな」という軽い気持ちで読んでみてくださいね。
病院の外来・検査部門
まず思い浮かぶのは、病院の中にある外来や、内視鏡室・放射線科などの検査部門ではないでしょうか。
| どんなところ? | 診察の補助や、検査の説明・介助、予約管理などが主な業務です。 患者さんは基本的に歩いて来られる方が多いですね。 |
|---|---|
| なぜ夜勤がない? | ほとんどの場合、診療時間や検査時間が日中に限られているため、夜勤はありません。 (※一部、救急外来などは除きます) 病院によっては「外来配属=救急外来も担当」という場合もあるので、どのような勤務形態になっているかは確認しておいてください。 |
| メリット | 生活リズムが安定する。基本的に土日祝日が休みの場合が多い。 様々な疾患の患者さんと関わる機会がある。 |
| デメリット/注意点 | 給与は病棟勤務より下がる傾向。 外来は待ち時間が長くなりがちで、患者さんからのクレーム対応が必要な場面も。 検査部門は専門的な知識・技術が求められる。 |
クリニック(診療所)
街中にあるクリニック(診療所)も、夜勤のない代表的な職場です。無床(入院ベッドがない)クリニックがほとんどですね。
| どんなところ? | 医師の診察補助、採血や点滴、検査の説明、受付業務の補助など、業務内容は多岐にわたります。地域に密着した医療を提供しています。 |
|---|---|
| なぜ夜勤がない? | ほとんどが入院施設を持たず、外来診療のみのため、夜勤はありません。 |
| メリット | 夜勤がなく、日曜・祝日休みのところが多い。 残業が比較的少ない傾向。 患者さんとの距離が近く、コミュニケーションを大切にできる。 |
| デメリット/注意点 | 給与水準は病院より低いことが多い。 スタッフ数が少ないため、人間関係が濃密になりやすい面も。 看護師としての業務範囲が限られると感じる人もいるかもしれません。 |
訪問看護ステーション
患者さんの自宅に訪問して看護ケアを提供する、訪問看護ステーションも、基本的には日勤が中心です。
| どんなところ? | バイタルサイン測定、医療処置(点滴、褥瘡ケアなど)、服薬管理、家族への指導など、在宅での療養生活をサポートします。 |
|---|---|
| なぜ夜勤がない? | 日中の訪問がメインですが、ステーションによってはオンコール体制(緊急時の電話対応や臨時訪問)があり、夜間や休日に対応が必要な場合があります。 完全な夜勤は少ないですが、オンコール担当になると待機が必要。 |
| メリット | 患者さん一人ひとりとじっくり向き合える。 自分の判断でケアを進める場面が多く、やりがいを感じやすい。 日勤中心で、比較的スケジュール調整がしやすい場合も。 |
| デメリット/注意点 | 一人で訪問し、判断・対応する場面が多いため、ある程度の臨床経験や判断力が求められる。 オンコール対応がある場合は、精神的な負担を感じることも。 給与はステーションによって様々。 |
健診センター
健康診断や人間ドックを専門に行う健診センターも、夜勤がない職場の一つです。
| どんなところ? | 採血、身長・体重測定、視力・聴力検査、心電図、医師の診察補助などが主な業務。 健康な方が対象です。 |
|---|---|
| なぜ夜勤がない? | 健診は基本的に日中に行われるため、夜勤はありません。 |
| メリット | 夜勤がなく、土日祝日休みの施設が多い。 残業も少ない傾向。 健康な方を対象とするため、精神的なプレッシャーは比較的少ない。 |
| デメリット/注意点 | ルーチンワークが多くなりがちで、看護師としてのスキルアップを感じにくい場合も。 採血の機会が非常に多い。 給与は低めの傾向。 |
美容クリニック など
その他にも、美容クリニック(脱毛、美肌治療など)、企業の健康管理室(産業看護師)、保育園、介護施設(デイサービスなど)といった職場も、夜勤がない、もしくは少ない働き方が可能です。 それぞれに専門性や特徴、メリット・デメリットがあります。
注意点:夜勤がない働き方のメリット・デメリット
ここまでいくつかの職場を紹介しましたが、夜勤のない働き方には、共通するメリットとデメリットがあります。



夜勤のない働き方は、魅力的に見えるかもしれませんが、メリットばかりではありません。
もし、あなたが将来的にこうした働き方を考える時が来たなら、給与面や業務内容、求められるスキルなどをよく比較検討し、自分にとって本当にそれがベストな選択なのか、慎重に考えることが大切ですよ。
新人看護師さんの夜勤や働き方に関するQ&A
ここまで記事を読んでくれて、ありがとうございます。 夜勤のきつさの理由から、具体的な対処法、そして少し視点を変えたメリットや、限界を感じた時の考え方までお話ししてきました。
それでも、「まだちょっとここが分からないな…」「こういう場合はどうなんだろう?」といった疑問や不安が残っているかもしれませんね。



そこで最後に、新人看護師さんから特によく聞かれる質問や、僕自身が「これ、新人の頃に知りたかったな…」と思うことなどを、Q&A形式でまとめてみました。 あなたの疑問解消のヒントになれば嬉しいです。
これで、よくある質問への答えは以上です。
あなたの疑問や不安が、少しでも解消されていたら嬉しいです。
まとめ:焦らず、諦めず、あなたらしい働き方を見つけよう
ここまで、本当に長い文章を最後まで読んでくれて、ありがとうございます。 新人看護師として、慣れない夜勤に悩み、不安を感じているあなたの気持ちに、少しでも寄り添えていたら嬉しいです。
この記事では、
- なぜ新人看護師の夜勤が特に「きつい」と感じるのか、そのリアルな理由
- 今すぐ試せる、具体的な10個の乗り越え方のコツ
- ちょっと視点を変えた、夜勤ならではのメリット
- どうしても限界を感じる前に試したいこと、相談できること
- (参考としての)夜勤のない働き方の選択肢
- よくある疑問や不安へのQ&A
といった内容をお話ししてきました。
改めて、一番伝えたいこと。 それは、夜勤を「きつい」と感じるのは、決してあなたが弱いからでも、看護師に向いていないからでもない、ということです。それは、あなたが真剣に仕事に向き合い、患者さんのことを考え、責任感を持って頑張っている証拠なんです。
そして、その“きつさ”は、工夫次第で必ず和らげることができます。 この記事で紹介した10個のコツ、全部を完璧にやる必要はありません。「これならできそうかな」と思うものを、まずは一つ、試してみてください。小さな工夫の積み重ねが、きっとあなたの夜勤を少しずつ楽にしてくれるはずです。
それでも、どうしても辛い時、しんどい時もあるでしょう。そんな時は、絶対に一人で抱え込まないでください。 あなたの周りには、話を聞いてくれる先輩、心配してくれる同期、そしてあなたの成長を願っている上司がいます。家族や友人も、きっとあなたの味方です。勇気を出して、あなたの気持ちを伝えてみてください。
今の場所で、工夫しながら頑張り続ける道。
相談して、働き方を調整してもらう道。
あるいは、心機一転、新しい環境を選ぶ道。
どの道を選ぶにしても、それはあなた自身の人生であり、あなた自身の選択です。どれが正解でどれが間違い、ということはありません。大切なのは、あなたが心身ともに健康で、自分らしくいられる働き方を見つけること。
僕自身、新人時代は本当に不器用で、失敗ばかりしていました。夜勤の前はいつも憂鬱で、「いつになったら慣れるんだろう…」と途方に暮れた日も数えきれません。
でも、周りの人に支えられ、少しずつ工夫を重ねる中で、なんとか乗り越えてきました。そして今、管理者として新人看護師さんたちと関わる中で、皆さんが悩みながらも一生懸命に頑張る姿を見て、「あの頃の自分と同じだな」と感じると同時に、心から「応援したい」「サポートしたい」と思っています!
だから、焦らないでください。諦めないでください。 あなたは一人ではありません。 あなたのペースで、一歩ずつ。あなたらしい看護師としての道を、見つけていってくださいね。



この記事が、そのための小さなきっかけとなれたなら、これほど嬉しいことはありません。
あなたが、これからも笑顔で看護の仕事に誇りを持って向き合っていけることを、心から応援しています!
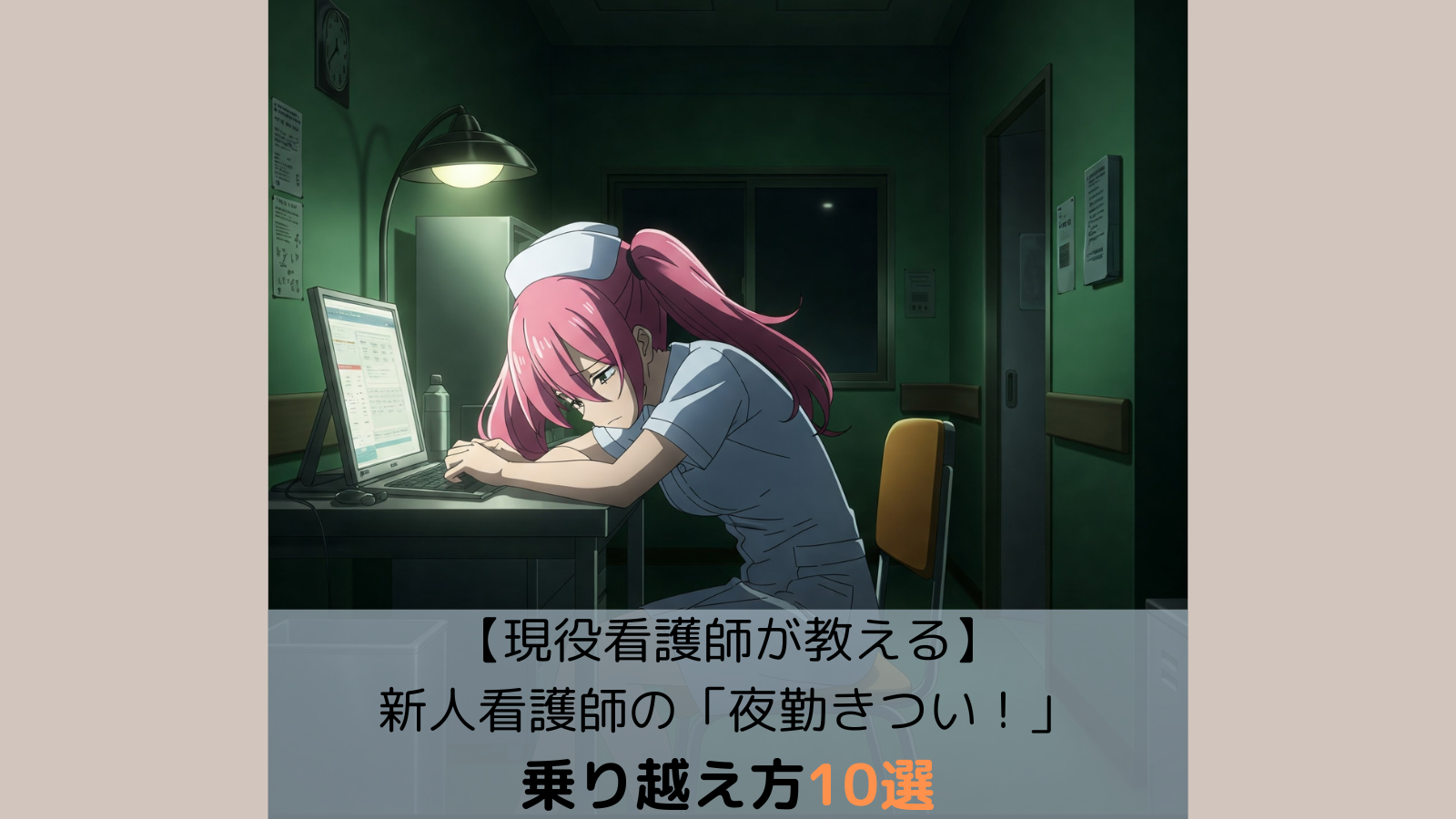
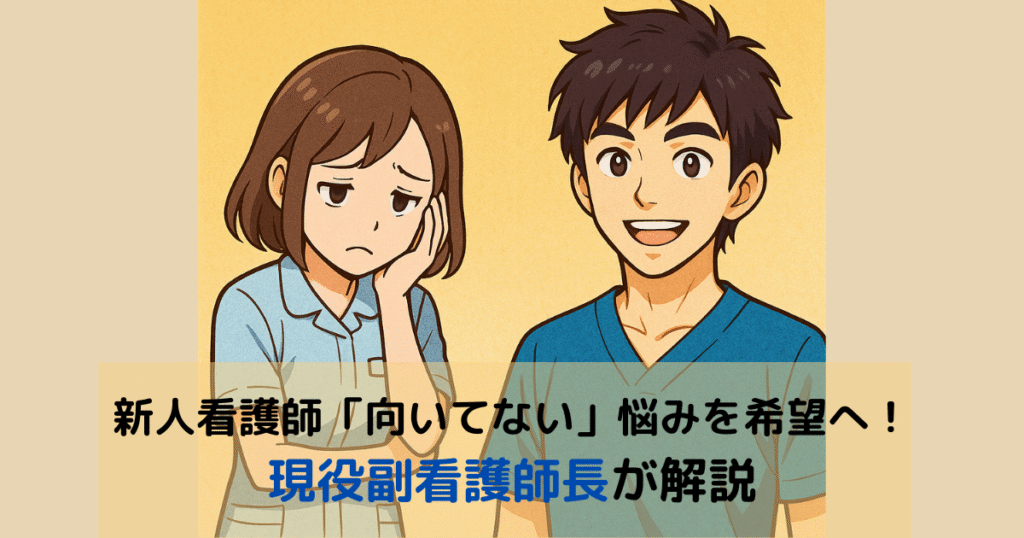
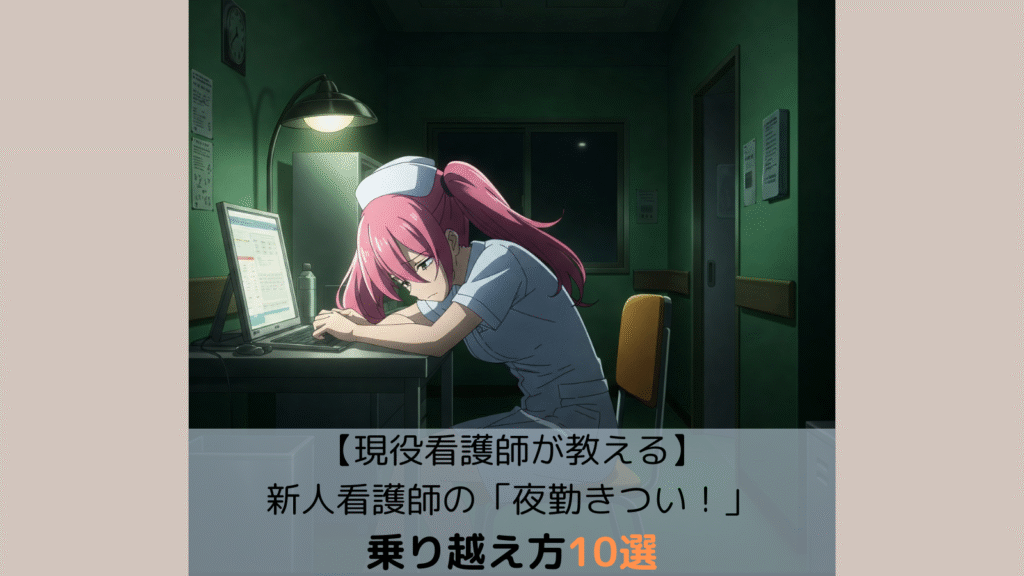


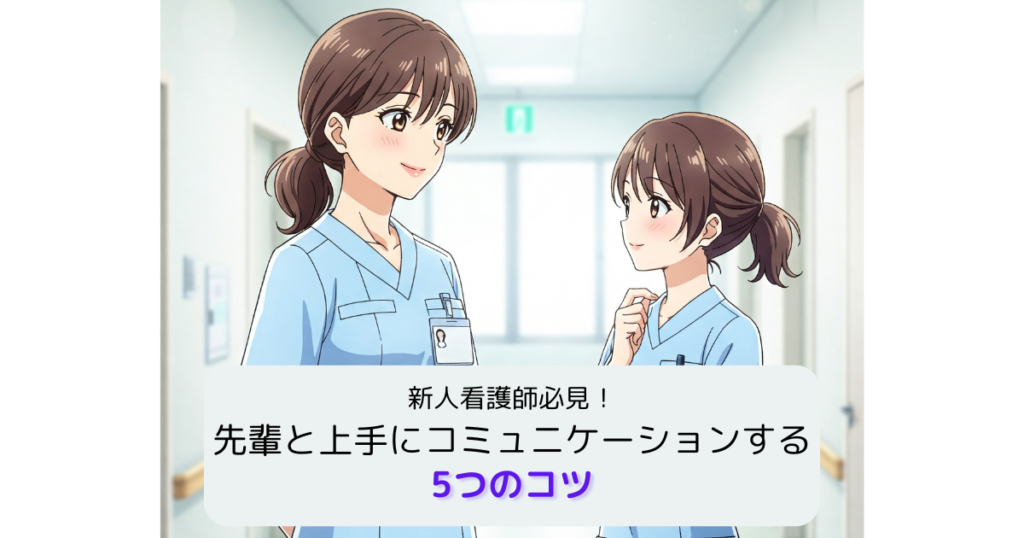
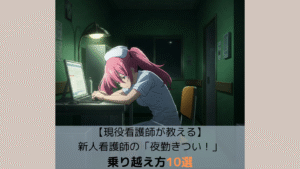

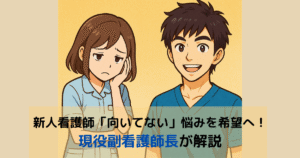


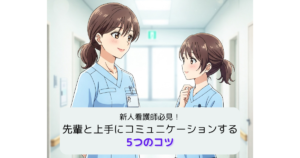
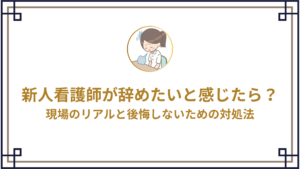
コメント